#3097-1 資本論と21世紀の経済学(改訂第2版)-1 Aug. 2, 2015 [99. 資本論と21世紀の経済学(2版)]
#3097 資本論と21世紀の経済学(改訂第2版)<目次> Aug. 2, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-08-15
=================================
資本論と21世紀の経済学
Ⅰ. 学の体系としての経済学
1. <デカルト/科学の方法四つの規則とユークリッド/『原論』>
『経済学批判要綱』(以下『要綱』と略記)流通過程分析や商品分析は「下向の旅」であり、『資本論』が商品の概念規定から始めるのは「上向の旅」である。これはデカルト『方法序説』(1637年)にある「科学の方法 四つの規則」にあるものと同じだけでなく、数学書であるユークリッド『原論』とも方法論において同じものである。集合論をベースにした現代数学の体系化の試みである『ブルバキ 数学原論』(東京図書)も、『資本論』と共に公理的構成の厳密な演繹的体系構造をもつ。
デカルト「科学の方法 四つの規則」には次のような解説がある。
------------------------------------------------------
デカルト『方法序説』ワイド版岩波文庫 「科学の方法 四つの規則」27ページ~
まだ若かった頃(ラ・フレーシュ学院時代)、哲学の諸部門のうちでは論理学を、数学のうちでは幾何学者の解析と代数学を、少し熱心に学んだ。しかし、それらを検討して次のことに気がついた。まず論理学は、その三段論法も他の大部分の教則も、未知のことを学ぶのに役立つのではなく、むしろ、既知のことを他人に説明したり、そればかりか、ルルスの術のように、知らないことを何の判断も加えず語るのに役立つばかりだ。…以上の理由でわたしはこの三つの学問(代数学、幾何学、論理学)の学問の長所を含みながら、その欠点を免れている何か他の方法を探究しなければ、と考えた。法律の数がやたらに多いと、しばしば悪徳に口実を与えるので、国家は、ごくわずかの法律が遵守されるときのほうがすっとよく統治される。同じように、論理学を構成しているおびただしい規則の代わりに、一度たりともそれから外れまいという堅い不変の決心をするなら、次の四つの規則で十分だと信じた。
第一は、わたしが明証的に真であると認めるのでなければ、どんなことも真として受け入れないこと、そして疑いをさしはさむ余地のまったくないほど明晰かつ判明に精神に現れるもの以外は何もわたしの判断の中に含めないこと。
第二は、わたしが検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分別すること。
第三は、わたしの思考を順序にしたがって導くこと。そこでは、もっとも単純でもっとも認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るようにして、もっとも複雑なものの認識まで昇っていき、自然のままでは互いに前後の順序がつかないものの間にさえも順序を想定しえ進むこと。
そして最後は、すべての場合に、完全な枚挙と全体にわたる見直しをして、なにも見落とさなかったと確信すること。
きわめて単純で容易な、推論の長い連鎖は、幾何学者たちがつねづね用いてどんなに難しい証明も完成する。それはわたしたちに次のことを思い描く機会をあたえてくれた。人間が認識しうるすべてのことがらは、同じやり方でつながり合っている、真でないいかなるものも真として受け入れることなく、一つのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなに遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなにはなれたものでも発見できる、と。それに、どれから始めるべきかを探すのに、わたしはたいして苦労しなかった。もっとも単純で、もっとも認識しやすいものから始めるべきだとすでに知っていたからだ。そしてそれまで学問で真理を探究してきたすべての人々のうちで、何らかの証明(つまり、いくつかの確実で明証的な論拠)を見出したのは数学者だけであったことを考えて、わたしはこれらの数学者が検討したのと同じ問題から始めるべきだと少しも疑わなかった。
*重要な語と文章は、要点を見やすくするため四角い枠で囲むかアンダーラインを引いた。
----------------------------------------------------
デカルトが「三つの学問(代数学、幾何学、論理学)」といっているが、歴史的順序に従えば「論理学、幾何学、代数学」である。アリストテレス論理学とユークリッド幾何学、ディオファントス代数学(『算術』)を指していると見ていいのだろう。デカルト自身が『幾何学』を著しているが、これは解析幾何学(曲線や立体のいろいろな性質を代数記号を用いて座標系を導入して研究する分野、中学・高校で習う座標平面のこと。XYZ座標をデカルト座標という)である。『方法序説』訳注#8で確認したが、やはり論理学はアリストテレス論理学。これには弁証法も含まれるが、ソクラテスの「弁証法」であって、弁論術であり、ヘーゲルのそれとは異なる。デカルトは解析幾何学や哲学や論理学の研究をした上で、『方法序説』で自分の方法論を振り返って記述している。科学の方法とは何かということを、『幾何学』を書いた後で帰納的に考えているのである、はじめに方法論ありきではない。
哲学者であり数学者であり物理学者でもあったデカルトがフランス語で書いた著作をマルクスが読んでいたかどうかはわからないが、『要綱』にも『経済学批判』にも『資本論』にも、わたしが読んだ限りでは、体系構成についてデカルトから学んだという記述は1行もない、もちろんユークリッド『原論』への言及もない、どちらとも接点はなさそうである。数に関して言うと『資本論』は有理数の四則演算だけで無理数は使われていない、そして『資本論』の約百年も前にできた微分積分も使われていないこととあわせ考えると、マルクスは数学への興味が薄かったと判断していい。
微積分にすら関心がなかったくらいだから、経験科学の分野である経済学全体が、そうではない純粋数学の体系化と同じ演繹的な方法で叙述可能だという自覚も見通しも当時のマルクスにはなかっただろうとわたしは推測する。
第1部だけでもフランス語版だけでなく、英語版の訳者へのマルクスの編集指示書が存在しており、それすらずいぶんと無視したくらいだから、エンゲルスに方法論を根本から見直す余裕がなかったのも事実だろう。第2部以降は悪筆のマルクスが残した膨大な遺稿から、『要綱』デッサン通りに第2部と第3部をエンゲルスがまとめたのだから、これは体系構成研究から除外してよい。
旧構想をそのまま踏襲したということは、経済学体系がどうあるべきかをエンゲルスが読み取ることができなかったことを意味している。エンゲルスが元にしたマルクスの資本論構想は1858年の『要綱』で示されていたものである。フランス語版の出版が1872年だから14年も間がある。
フランス語版編集時点で全体の見通しがあったかどうかはわからない。マルクスは構想を大きく変えたか、見通しがまったく立たないままだったかのどちらかだが、資本論第2部の編集方針については何も書き残していない。それゆえわたしたちは『要綱』『資本論初版』そしてマルクスが編集を直接指示したフランス語版の「第一部」の内容から、内在的な論理に従って体系構成がどうあるべきかを読み取らなければならない。
ヨーロッパの学問の伝統という点からは、科学の方法(=人文科学をも含む学問の方法)にはアリストテレス論理学とユークリッド「原論」が燦然と輝いている。経済学の体系構成を考えるということは、そういうヨーロッパの学問の伝統線上にマルクス『資本論』を措定したときに何が見えてくるのか、という問題でもある。
『資本論』は経済学的概念の構造物なのだが、書かれた文章から使われているいくつかの概念の関係を抽象的な構造物としてイメージするのはむずかしい。言葉をイメージに変換するのにハードルが一つあり、さらにそのイメージを今度は別の具体的な言葉に変換して説明するために、もう一つのハードルが待ち受けている。ひょんなことから、ユークリッド『原論』を読み、数学の体系と経済学諸概念の体系が似ていることに気がついた、これなら、アナロジー(類推)が可能だし、説明も楽になる。修士論文を書いていたときにそのことに気がついていたら、大学に残る決意を固めただろうが、不勉強で気がつかなかった。
2. <体系構成法の視点から見たユークリッド『原論』>
高校生には「ユークリッドの互除法」が教科書に載っているから馴染みがあるだろう。ユークリッドの人物についてはどこで生まれてどこで育ったのか、記録が残っていない。しかし、実在したことだけは確かである。アルキメデス(287年ごろ~212B.C.)がその著「『球と円柱について』の第1巻の第2命題の証明の中で「ユークリッド(の『原論』)の第1巻命題2により」と記してある。
(ユークリッド『原論』より、「ユークリッドと『原論』の歴史」437㌻。訳・解説 中村幸四郎・寺阪英孝・伊藤俊太郎・池田美恵 共立出版社1971年初版、以下『原論』と略記)
ユークリッドはイデア論で有名なプラトンの直弟子たちと同世代である。
『原論』は公理・公準の説明に続いて、同じ半径の円を二つ使った正三角形の作図から幾何学の解説を始めている。第1巻は平面図形の性質がとりあげられている。『原論』は平面幾何学だけではない、数論や立体幾何学、正多面体にまで及ぶ。第7~9巻は「数論」を扱っている。ここで面白いのは、線分の長さの区切りに数字ではなく文字が充てられている点で、広義の意味での代数学も含まれていると考えてよいのだろう。第7巻の冒頭には23個の定義が並んでいる。大雑把にその順序を書くと次のようになる。
単位⇒数⇒割り切れる数と割り切れない数⇒約数⇒偶数と奇数⇒偶数や奇数の除算の商の分類⇒素数の定義⇒互いに素⇒素数と合成数⇒平面数:二つの数の積で表される数⇒立体数:三つの数の積で表される数⇒平方数:等しい数に等しい数をかけたもの⇒立法数⇒比例数⇒相似な平面数と立体数は比例する辺をもつ数である⇒完全数:自分自身の約数の和に等しい数
数論の定義は単純なものから複雑なものへという順序で並んでいる。
最終巻の13巻第16章では正二十面体がとりあげられている。
「正二十面体をつくり、先の図形のように球によって囲み、そして正二十面体の辺が劣線分とよばれる無理線分であることを証明すること」(『原論』427頁)
立体図形、しかも正二十面体の辺が有理数ではなく無理数であることを証明せよというのである。球の直径を有理線分(有理数)としたときに20個の等辺三角形(正三角形)の各辺の長さが無理線分(無理数)になる証明が載っている。
『原論』は平面幾何学と数論そして立体幾何学に及んでいる。全体が統一の取れた体系というよりは、いくつかの部分に分かれているといったほうが事実に即しているだろうか。全体の展開順序はこのようになっている。
平面幾何⇒数論⇒立体幾何
平面幾何と立体幾何の間に数論の挟まっているのがどうにも不細工にみえるが、数論を扱わぬわけにもいかない。平面図形の中に、無理数の背理法での証明や三平方の定理が載っているが、数論として独立に扱えるものではなく、平面図形に付随して扱われただけ。計算が複雑になるに及んで、立体図形の前に数論として独立に扱わざるを得なくなったという事情があるのだろう。
平面に高さという要素を加えたものが立体であるから、単純さを尺度にすると、次の不等式が成り立つ。
平面図形<立体図形
ここでも単純なものからより複雑なものへという展開系列の順序が守られている。
第1巻の平面幾何は、重なり合う半径の同じ二つの円で等辺三角形を描くことから始められている。平面を二つの線分で囲むことはできない、三本の線分で囲まれた三角形がもっとも単純な平面図形である。三角形の内では等辺三角形がもっともシンプルで美しい。三角形を3分類して並べると、「等辺三角形⇒二等辺三角形⇒不等辺三角形」の順序になるが、第1巻は等辺三角形のあとに三角形の等積変形が来て、そして平行線の性質が導かれている。
マルクス『資本論』との関係でいうと、注目すべきは公理・公準と作図の展開順序の2点に絞られる。第1巻の図形の性質は、もっとも単純な平面図形、(半径の同じ円二つを使った)正三角形の作図が最初におかれている。数論の定義の並び順も「単純なものから複雑なものへ」という系列になっていることはもうお分かりだろう。
第1巻は「定義」⇒「公準」⇒「公理」⇒単純な図形の作図(正三角形)という順に展開されている。定義は23個あり、公準(要請)は5個、公理(共通概念)は9個並んでいる。定義は「点⇒線⇒線の端⇒直線⇒面⇒平面⇒…⇒平行線」
公準(要請) 次のことが要請されているとせよ。
1. 任意の点から任意の点へ直線を引くこと。
2. および有限直線を連続して一直線に延長すること。
3. および任意の点と距離(半径)とをもって円を描くこと。
4. およびすべての直角は互いに等しいこと。
5. および1直線が2直線に交わり同じ側の内角の和を2直角より小さくするならば、この2直線は限りなく延長されると2直角より小さい角のある側において交わること。
公理(共通概念)
1.同じものに等しいものはまた互いに等しい。
2.また等しいものに等しいものが加えられれば、全体は等しい。
3.また等しいものから等しいものがひかれれば、残りは等しい。
4.また不等なものに等しいものが加えられれば全体は不等である。
5.また同じものの2倍は等しい。
6.またおなじものの半分は互いに等しい。
7.また互いに重なり合うものは互いに等しい。
8.また全体は部分より大きい。
9.また2線分は面積を囲まない。
平行線公準が成り立たないものと前提すると、リーマン球面幾何学のような非ユークリッド幾何学が成立することから、『資本論』の公理・公準の一部を入れ替えると別の経済学が生まれる可能性があることは容易に予想がつく。そういう操作を大学院生の頃から考えていたが、当時は何をどのように換えたらいいのかわからなかった。
中学校と高校の図書室にはこのユークリッド『原論』を備えてもらいたい、そして数学の先生はそういう本が自分の学校の図書室にあることを生徒に伝えてもらいたい。数学好きの早熟な生徒なら十分に読める。田舎の学校でも、工夫次第で都会の学校よりもいい環境を整えることができる。大人の責任を果たすために、できることから始めてもらいたい。
3. <マルクスが『資本論』で何をやりつつあったかを読み解く>
マルクスが資本論で何をしようとしたのかについては定説がない。マルクス自身が資本論第1部を書いて、そのあと草稿を書き散らしただけで、どのようにまとめたらいいのかわからないと吐露している。だから、1858年に書かれた『要綱』段階のマルクスの構想で資本論を整理してはいけない、マルクス自身が1866年に体系の見通しが立たなくなったとエンゲルス宛に書いているのだから、その言を尊重すべきであり、マルクスがなぜ行き詰ったのかを合理的に説明できなければならない。この大きな謎を解いた経済学者はいない。謎を解く鍵はヘーゲル弁証法にある。経済学体系構成にヘーゲル弁証法を利用したのはプルードンとマルクス二人だけである、後にも先にも例がない。
マルクスは研究が行き詰ったことをエンゲルスへの手紙で吐露しただけだから、彼が資本論で何を目論んだのか本当のところがわからないままである。だから、エンゲルスが古い構想に基づいて第2部以降を編集したように、他の経済学者が資本論を読んで独自の理論体系を構築する余地が残された。
たとえば、マルクス経済学では宇野シューレが最大派閥であるが、宇野弘蔵は理論構成を三段階(原理論・段階論・現状分析論)に分け、資本論を経済学原理論と位置づけた。『要綱』日本語版が出版されていない段階での研究だから、マルクスがやって見せた下向分析の過程を丹念に追わずに、結果の『資本論』を徹底的に読み込んで自分なりの思考を重ね、別の理論体系をつくってしまった。これはこれで面白い。宇野氏は『資本論初版』序文にある、次の章句を何度も読み返し、塾考を重ねたのだろう。
「物理学者は、自然過程を観察するにさいしては、それが最も内容の充実した形態で、しかも撹乱的な影響によって不純にされることが最も少ない状態で観察するか、または、もし可能ならば、過程の純粋な進行を保証する諸条件の下で実験を行う。この著作で私が研究しなければならないのは、資本主義的生産様式であり、これに対応する生産関係と交易関係である。その典型的な場所は、今日までのところイギリスである。これこそは、イギリスが私の理論的展開の主要な例解として役立つことの理由なのである。」
マルクスの『資本論』を読めば読むほど迷路を彷徨うことになる、わたしは高校2年生のときにそういう強烈な体験をした。大きな森の中に入り込んで方角を失ったのである。それ以来、この巨大な知の森にもう一度分け入り、通り抜けてみたいと思い続けた。見通しがつくまでなんと約40年も掛かってしまった。
大御所の宇野弘蔵はマルクスが『資本論』を書いている途中で、肝心の体系構成の方法論で破綻したとは考えなかった。マルクスは『資本論初版』第一部を書き上げて、自分の方法論の破綻に気がついてしまった。だから、エンゲルスに第2部以降の体系化はとても無理だと手紙で書き遺したのである。実際に第2部以降の体系化作業をやることはなかった。
マルクスの時代には資本の原始蓄積が始まったのは18世紀英国で、資本主義の最初の典型例であった。その後百年たった19世紀中葉の米国では北部工業地帯で原始蓄積が始まり、南部の奴隷を工場労働者として労働市場へ投入する必要が生じた。いま資本の原始蓄積過程にあるのは中国やインドである。原始蓄積が始まれば、労働者の雇用数が増大し、賃金が高騰する。だが、それは資本蓄積を阻害することのない範囲であるとマルクスは「第七編 資本の蓄積」で指摘している。資本蓄積の進行は労賃変動の根源である。英国が研究対象となったのは当然である。
宇野『価値論』は読むほうが辟易するくらいしつこいが、しつこいからこそ独自の理論体系を造り、大きな学閥となりえた。わたしは宇野氏の『価値論』の論理展開しつこさに辟易すると同時に敬意を払いたい、たとえ見当違いの方向に行ったとしても、学者はあれぐらいしつこくなければいけない。
宇野弘蔵『経済学方法論』について、宇野学派の馬場宏治先生が感想をもらしている。
方法論については馬場先生のいう通りだと思う。マルクスもヘーゲル弁証法を真正面に押し捲ったが、研究が進んでくるとヘーゲル弁証法とは違うところにでてしまった。あとから自分の研究過程をみて、方法はこうだと書けばよかったのだろう。そこでマルクスに代わってその作業を試みるのがこの論考の主要な目的の一つである。
宇野氏が数学に興味があるかあるいは『要綱』が出版されていれば、丹念に読んで別の理論体系を構築した可能性はある、それにしても、宇野氏はドイツ語を読むのにそれほど困難があったわけではないから、『要綱』をドイツ語版で読めばよかったのだ。『経済学批判』と『資本論』を読んでいれば十分だと判断したのだろうか、わたしにはその点が疑問である。
4. <資本論体系の特異性とプルードン「系列の弁証法」>
一番大事な点:資本論は数学と同じ演繹的体系をなしている。
経済学が経験科学なら、データに基づいて帰納的に法則を導き出し、理論を構築するのという方法論をとるはずだが、マルクスはそうはしなかった。はじめに方法論ありきだった。
経済学の研究という点から見るとじつに運のよいことにマルクスは1849年に英国に亡命し、1850年から大英図書館で経済学の研究をし始める。A.スミス『諸国民の富』やD.リカード『経済学および課税の原理』はよく読みこんでいる。経済学の本を読み、経済学の基本概念はなにか、その相互関係はどうなっているのかということに関心をもち何年間も執拗に追い続けたようで、その跡が著作年表や一連の著作から読みとれる。1858年『経済学批判要綱』(以下『要綱』と略記)での、「流通過程分析⇒価値形態(価値表現形式)⇒商品の基本概念分析」に下向分析の足跡がはっきり記されている。資本の原始蓄積過程における生産性上昇による生産力増大、そして資本の加速的な増殖が労賃の高騰を招くというような法則性抽出は、データの読みと内省的な思考の結果である。
ヘーゲル哲学にとらわれすぎると、それを超えたところにある『資本論』体系が見えなくなる。ヘーゲル哲学に戻って考える必要はない。『資本論』第1部をよく読めばいいのである。
方法論に注目すると、同時代のピエール・ジョセフ・プルードン(1809/1/15-18651/19、マルクスより9歳年上)に系列の弁証法がある。プルードンの論理的系列は思考作用の抽象過程をあらわすものであると同時に、「その結果としてえられる抽象的・一般的な概念の構造を表す」(佐藤茂行著『プルードン研究』109ページ、昭和50年出版)ものであると考えていた。アンダーラインを引いた箇所は、そのまま『資本論』に当てはまる。
プルードンはフランス人だからデカルト『方法序説』(いまでも高校国語の教材に採り上げられている)は読んでいるはずで、その延長上に自分の思考を積み重ねたのだろう。デカルトよりは踏み込んでいる。弁証法がこの時代の流行だったのだろう、しかし、ヘーゲル弁証法という余計な夾雑物が混じることで上向の論理の道をプルードンもマルクスも踏み外してしまった。
A.スミスが諸国民の富の原因と性質を明らかにするものとして経済学を捉えたのに対してプルードンは貧困を実証する手段として捉えた。そして自らの経済学体系を「系列の(ヘーゲル)弁証法」で叙述したのである。
---------------------------------------------
「「経済学」を貧困の原因の探求の科学としてではなく、貧困の実証の科学として評価するに至ったのであった。言いかえると、これまでの経過から判明するように、プルードンが経済学研究に取り組んだ際の問題関心は、現実的な「条件と財産の不平等」の究明であった。パリでの研究を通じて、かれにとって「経済学」は、この「不平等」の原因を究明する手段ではなく、これを実証する手段として、そしてその限りで有効なものとして評価されるに至ったわけである。」同書188ページ
「プルードンの経済学体系は、平等=正義を分類主題として、「政治経済学」のカテゴリーを批判的に再編成した、いわば古典経済学批判の体系である。そこでは、まず、「分業」「機械」「競争」などのカテゴリー(類概念)が、平等=正義を区分原理として、それに対する肯定と否定の規定(種概念)にあらかじめ二分されている。…このようにして、相互に「アンチノミー」の関係にある概念の系列、すなわち「矛盾」の体系が成立する。…以上のような体系の構成の原理は、1843年の『人類における秩序の創造について』の中の「系列の弁証法」によって確立していたのであった。」同書238ページ
---------------------------------------------
アンダーラインを引いたところは『資本論』商品章の価値と使用価値が相互にアンチノミーの関係にある概念として扱われ、価値形態でそれが交換価値と使用価値という概念の系列となって現れている。しかし、一連の著作の中でマルクスは系列の弁証法に一度も言及していない。プルードンの『人類における秩序の創造』(以下『創造』と略記)は資本論初版よりも24年も前に書かれている。マルクスが最初の経済学に関する著作『経済学・哲学草稿』を出版したのが26歳1844年、つまりプルードンの『創造』の1年後のことになる。プルードンのこの著作のドイツ語版があったのかどうかは書誌学者の研究に任せたい。
方法論としてはほとんど同じであるのに言及していないというのは、この場合は利用したと受け取っていいのだろう。シンプルに言うと、プルードンの「系列」とは上向の系列であると理解してよい。マルクスが上向論理で行き詰ったのは、系列の弁証法を意識したか、同じことだがヘーゲル弁証法を『資本論』の論理展開エンジンに用いたためであるように思う。それはまったく必要のないことだった。
アナーキストのプルードンとは、思想においても方法論においても、コミュニズムを提唱したマルクスは明確な線を引いておきたかったのではないか。マルクスは古典派経済学から学び、その基本的な概念を析出しそれらの相互関係を突き止める作業が必要だった。そこさえきっちり押さえれば、系列の順序はおのずから明らかになった。『要綱』がそういう研究過程を明らかにしてくれているから、プルードンの系列の弁証法から学ぶ必要はなかった。
『資本論』研究文献でプルードンの系列の弁証法に言及したものを見たことがない。体系構成についてプルードンとの比較分析の余地がある。
ついでだから、もうすこし掘り下げて具体的に論じてみたい。1866年のエンゲルス宛の手紙にあるように、マルクスには上向の系列が途中から見えなくなったことがわかる。事実に即して言えば、交換関係から貨幣を媒介として生産関係へと概念的関係を拡張した後、どのように体系を記述すればいいのかわからなくなった。下向分析で見つかった上向系列が生産関係で行き止まってしまった。単純な市場関係を展開した後、「国内市場と国際市場」関係へと概念的関係を拡張し、世界市場関係へと至る道がマルクスの採るべき上向系列だった。ところが、資本論初版が出版された1867年にはまだ世界市場は出現していない、そこに気がついて困惑した可能性がある。マルクスの時代に『資本論』を完成することは無理だった、世界市場は実証研究がその背後になければ描きえないのである。あの時代にはリカードの比較生産費説があるだけだったが、それで世界市場を描くことはできない、貧弱すぎるのである。この点から、経済学は経験科学の一つで、なおかつ演繹的体系構成をもつ面白い学問分野であることがわかる。
院生のとき、リカードの国際市場論について小論を書いた。その折にマルクス『資本論』と比較しながらリカード『経済学および課税の原理』を読んだ。修論で『資本論』の体系構成の最後の環である世界市場関係に見通しをつけるために、リカードの国際市場論は一度読んでまとめ、中身の検討をすべきだと考えていたのだが、単純な国際市場関係とその完成形態である世界市場関係を概念的に区別するとしたらどうなるのかまったく見通しが立たなかったのである。もちろん、今日のグローバリズムや機械とコンピュータとインターネットが融合したサイバー空間が現実の世界にあるはずもなく、不可能だったと言わざるをえない。そのころからマルクスの労働観への違和感も大きくなりつつあった。
5. <労働観と仕事観:過去⇒現在⇒未来>
奴隷制社会と農奴制社会を経験しているヨーロッパおよび中国、借金を返済できずに隷属民となる例はあるが奴隷制社会を経験していない日本は労働観に決定的な違いがあることを指摘しておきたい。労働は苦役であるというのは特殊ヨーロッパ的あるいは中国的な労働観であり、普遍性をもちえない。それぞれの地域において歴史的にさまざまな労働観が育まれたのだろうと思う。
古代ギリシア都市国家においては労働をするのは奴隷だった。特権市民は労働しない。その伝統は帝政ローマへも引き継がれた。こうしたヨーロッパの歴史が労働への蔑視を生んだのではないか。
わが国では国が成り立つ以前の縄文時代から続いている村落共同体のあり方も、働くことや仕事に対する考え方の違いを生み出したように見えるので、横道にそれて第23章「村落共同体と税:自由民と農奴」で取り上げる。
古代エジプトやメソポタミア、インド、中国ではどうだっただろう。こういう風に並べてみると「特殊ヨーロッパ的な労働観」の意味がいっそう鮮明になる。
この小論のテーマに関連する限りでは、ヨーロッパの労働観を取り上げるだけで十分だろう。
【過去系列】
(1) 古代都市国家およびローマ帝国での特権市民と奴隷や農奴
(2) 初期:東ヨーロッパ人の奴隷化:貿易支払いのための奴隷狩り
(3) アフリカ人の奴隷化
(4) 第一次産業革命
(5) 米国南部での奴隷需要増大
(6) 米国北部工業地帯で労働力商品の不足状況の現出 奴隷解放(1862年)=安価な労働力商品として黒人奴隷を解放して、北部工業地帯の労働力需要を満たす⇒ 米国の生産力の飛躍的拡大と世界支配開始
(7) 資本主義の第2段階開始:米国の勃興と白人帝国の世界支配の時代⇒帝国主義と植民地化政策資源収奪や低価格での一次産品収奪のための植民地政策。
(8) 白人帝国主義国家対アジアの戦い:日露戦争で有色人種の国が白人帝国に世界初勝利 (9) 大東亜戦争での日本の敗北と、日本の戦いに意を強くしたアジア各国が白人大国から次々に独立。
【現在進行系列】
(10) グローバリゼーションの時代:米国製ルールの押し付け
(11) 第二次産業革命:機械とコンピュータとインターネットが融合する時代。それ以前に比べて工場の生産性が数十倍になる。企業間競争の主戦場はソフトウェアとサイバー空間へ移る。
(12) 東アジアとインドへ覇権がシフトしていく
【未来系列】
(13) 第三次産業革命の時代(百年後):量子コンピュータネットワークの世界。
現在の性能向上速度を延長すると、コンピュータの性能は百年後に現在の2億倍になる。物の生産に人間の手は要らない時代となる。現在のコンピュータの2億倍の性能を持つ人工知能がわずか5cmのキューブサイズになる。ネットワークにつながれた人工知能とロボットが工場生産のすべてを支えるから、生産に人間が邪魔になる時代、人間の存在理由がなくなりかねない危ない世界でもある。どれほど優れた人間よりも、人工知能搭載人型ロボットのほうがはるかに性能がよい製品をつくり、さまざまなサービスを提供する世界が現出してしまったら、人間は労働者でも職人でもいられなくなる。コンピュータの処理速度や記憶容量が2億倍にもなってしまったら、人工知能搭載の人型ロボットと競争しても、性能の面でもコストの面でも人間が勝てるわけのない時代の幕が開けてしまう、百年後の人類はどうやって職を探すのだろう?量子コンピュータがパンドラの箱を開ける鍵でないことを願うが、便利さを追い求め、欲望の拡大再生産を続ける人間が自らの手で経済成長や利便性追及を止めることができるのだろうか?強い懸念を表明せざるをえない。
こうして過去・現在・未来の系列を俯瞰してみると、無限に自己増殖する資本はまるで癌細胞のようで、未来が人類にとってこういう風に悲観的なものだとしても、わたしたちは資本の自己増殖をとめることができるのだろうか?
資本の増殖の背後には人間の欲望の無限の自己増殖があるのだが、人間のコントロールを超えて資本が自己増殖する時代がコンピュータとネットワークの進化によって百年経たないうちに来る。
過去30年間のコンピュータの計算速度とメモリーの拡大速度を前提にすると、おおよそ百年後に処理速度も記憶容量も2億倍になり、コンピュータもネットワークも人間のコントロールを離れてしまう。コンピュータとネットワークとそれに接続されたさまざまな機械が人間のコントロールを離れて自立的に動く世界、そしてそれをとめるすべはおそらく人間にはない。
これから一世代、どんなに遅くとも二世代の間に、小欲知足の価値観に基づき、肉体を使う仕事へ回帰して、過剰な便利さを排除する、職人中心の経済社会を創るべきなのだろう。無限の成長は癌細胞の成長そのものである、経済成長を追い続けることをやめるべきだとわたしは思う。
その一方で、生物進化が必然だと仮定すれば、人類は経済成長と利便性の追及の果に絶滅する運命にあるのではないかとも考える。人類には自らの欲望を抑える叡智があるだろうか。
5. 数学者藤原正彦氏の示唆
数学者とはすごいものだ。慧眼の数学者は岡潔だけではなかった。一つの学問分野を深く掘り抜けば、他の分野へも通底するものがある。
藤原正彦はA.スミスの経済学へ次のような根本的な疑問を投げかけている。わたしは経済学にこのような根本的な疑問を投げかけた経済学者を寡聞にして知らない。
(アダム・スミスの)予定調和でこの社会が巧く回っていく、と。しかし、そこにあるのは結局は経済の論理だけなんです。人間の幸福ということはどこにもない。市場経済もまったく同じです。いま、何をするにも「消費者のため」と言いますよね。消費者がよいものを安く買えることがもっとも大切だ。たとえばお米を安くするためには自由貿易を推進してお米をどんどん輸入するのがよい。そうすると日本から百姓はいなくなって、美しい田園が全部なくなってしまいますが、そうなっても仕方がない。消費者が半分の値段でお米を買えればいいじゃないかと、そういう論理です。
はっきり言ってしまうと、経済学の前提自体が根本的に間違っている。人間の幸福ということは全く考慮にない。人間の金銭欲のみに注目し、個人や国家の富をいかにして最大にするしか考えていない。ものすごい天才が出てきて、経済学を根本的に書きかえてもらわないと、地球はもたないと思います。
産業革命以来、西欧は論理、合理を追求しすぎて、「人間の幸福」ということを全部忘れてしまった。(106ページ)
この箇所を読んだとき、日本の経済学者は誰一人このことに気づいていないのに、なぜ数学者である藤原正彦氏が気づいたのか、その目の確かさに驚いた。
ユークリッド原論は数学者の常識に属するから、経済学の出発点の誤りが体系全体の及んでいるというのは学問体系の相似性から言いうることで、むしろ当たり前のことだったが、経済に関心をもつすぐれた数学者がいなかった。
その一方で次のような疑問がわく。経済学者、とりわけ日本の経済学者はなぜこのことに気づかなかったのだろう?
簡単に言えば自分の頭で考えていないからだろう。ある種の能力がないとも言い切ってよいかもしれない。スミスやリカードの目でしか経済現象を見ていない、誰一人自分の目で見ていないのである。どこか学問をやる根本的な視点がずれている。経済学に限らずそういう「学者」が多いのは事実だろう。話はそれるが林望『知性の磨き方』(PHP新書)を読んだときにも、学問への姿勢に違和感を感じた。
「#969 日本人の矜持(2):経済学への示唆」より転載
=================================
* #1454 異質な経済学の展望 :パラダイムシフト Mar. 31, 2011
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2011-03-31
#2784 百年後のコンピュータの性能 Aug. 22, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-08-22
#2779 『ソードアートオンライン 9 』:量子コンピュータ・オンラインゲームと心 Aug. 17, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-08-17-1
#2804 『ソードアート・オンライン14』 Sep. 12, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-09-13
#2882 ソードアートオンライン007 マザーズロザリオ Nov. 26, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-11-26
#3217 日本の商道徳と原始仏教経典 Jan. 7, 2016
<8/2 ポイント配分割合変更>
100% 0% 0%

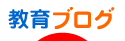

http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-08-15
=================================
資本論と21世紀の経済学
Ⅰ. 学の体系としての経済学
1. <デカルト/科学の方法四つの規則とユークリッド/『原論』>
『経済学批判要綱』(以下『要綱』と略記)流通過程分析や商品分析は「下向の旅」であり、『資本論』が商品の概念規定から始めるのは「上向の旅」である。これはデカルト『方法序説』(1637年)にある「科学の方法 四つの規則」にあるものと同じだけでなく、数学書であるユークリッド『原論』とも方法論において同じものである。集合論をベースにした現代数学の体系化の試みである『ブルバキ 数学原論』(東京図書)も、『資本論』と共に公理的構成の厳密な演繹的体系構造をもつ。
デカルト「科学の方法 四つの規則」には次のような解説がある。
------------------------------------------------------
デカルト『方法序説』ワイド版岩波文庫 「科学の方法 四つの規則」27ページ~
まだ若かった頃(ラ・フレーシュ学院時代)、哲学の諸部門のうちでは論理学を、数学のうちでは幾何学者の解析と代数学を、少し熱心に学んだ。しかし、それらを検討して次のことに気がついた。まず論理学は、その三段論法も他の大部分の教則も、未知のことを学ぶのに役立つのではなく、むしろ、既知のことを他人に説明したり、そればかりか、ルルスの術のように、知らないことを何の判断も加えず語るのに役立つばかりだ。…以上の理由でわたしはこの三つの学問(代数学、幾何学、論理学)の学問の長所を含みながら、その欠点を免れている何か他の方法を探究しなければ、と考えた。法律の数がやたらに多いと、しばしば悪徳に口実を与えるので、国家は、ごくわずかの法律が遵守されるときのほうがすっとよく統治される。同じように、論理学を構成しているおびただしい規則の代わりに、一度たりともそれから外れまいという堅い不変の決心をするなら、次の四つの規則で十分だと信じた。
第一は、わたしが明証的に真であると認めるのでなければ、どんなことも真として受け入れないこと、そして疑いをさしはさむ余地のまったくないほど明晰かつ判明に精神に現れるもの以外は何もわたしの判断の中に含めないこと。
第二は、わたしが検討する難問の一つ一つを、できるだけ多くの、しかも問題をよりよく解くために必要なだけの小部分に分別すること。
第三は、わたしの思考を順序にしたがって導くこと。そこでは、もっとも単純でもっとも認識しやすいものから始めて、少しずつ、階段を昇るようにして、もっとも複雑なものの認識まで昇っていき、自然のままでは互いに前後の順序がつかないものの間にさえも順序を想定しえ進むこと。
そして最後は、すべての場合に、完全な枚挙と全体にわたる見直しをして、なにも見落とさなかったと確信すること。
きわめて単純で容易な、推論の長い連鎖は、幾何学者たちがつねづね用いてどんなに難しい証明も完成する。それはわたしたちに次のことを思い描く機会をあたえてくれた。人間が認識しうるすべてのことがらは、同じやり方でつながり合っている、真でないいかなるものも真として受け入れることなく、一つのことから他のことを演繹するのに必要な順序をつねに守りさえすれば、どんなに遠く離れたものにも結局は到達できるし、どんなにはなれたものでも発見できる、と。それに、どれから始めるべきかを探すのに、わたしはたいして苦労しなかった。もっとも単純で、もっとも認識しやすいものから始めるべきだとすでに知っていたからだ。そしてそれまで学問で真理を探究してきたすべての人々のうちで、何らかの証明(つまり、いくつかの確実で明証的な論拠)を見出したのは数学者だけであったことを考えて、わたしはこれらの数学者が検討したのと同じ問題から始めるべきだと少しも疑わなかった。
*重要な語と文章は、要点を見やすくするため四角い枠で囲むかアンダーラインを引いた。
----------------------------------------------------
デカルトが「三つの学問(代数学、幾何学、論理学)」といっているが、歴史的順序に従えば「論理学、幾何学、代数学」である。アリストテレス論理学とユークリッド幾何学、ディオファントス代数学(『算術』)を指していると見ていいのだろう。デカルト自身が『幾何学』を著しているが、これは解析幾何学(曲線や立体のいろいろな性質を代数記号を用いて座標系を導入して研究する分野、中学・高校で習う座標平面のこと。XYZ座標をデカルト座標という)である。『方法序説』訳注#8で確認したが、やはり論理学はアリストテレス論理学。これには弁証法も含まれるが、ソクラテスの「弁証法」であって、弁論術であり、ヘーゲルのそれとは異なる。デカルトは解析幾何学や哲学や論理学の研究をした上で、『方法序説』で自分の方法論を振り返って記述している。科学の方法とは何かということを、『幾何学』を書いた後で帰納的に考えているのである、はじめに方法論ありきではない。
哲学者であり数学者であり物理学者でもあったデカルトがフランス語で書いた著作をマルクスが読んでいたかどうかはわからないが、『要綱』にも『経済学批判』にも『資本論』にも、わたしが読んだ限りでは、体系構成についてデカルトから学んだという記述は1行もない、もちろんユークリッド『原論』への言及もない、どちらとも接点はなさそうである。数に関して言うと『資本論』は有理数の四則演算だけで無理数は使われていない、そして『資本論』の約百年も前にできた微分積分も使われていないこととあわせ考えると、マルクスは数学への興味が薄かったと判断していい。
微積分にすら関心がなかったくらいだから、経験科学の分野である経済学全体が、そうではない純粋数学の体系化と同じ演繹的な方法で叙述可能だという自覚も見通しも当時のマルクスにはなかっただろうとわたしは推測する。
第1部だけでもフランス語版だけでなく、英語版の訳者へのマルクスの編集指示書が存在しており、それすらずいぶんと無視したくらいだから、エンゲルスに方法論を根本から見直す余裕がなかったのも事実だろう。第2部以降は悪筆のマルクスが残した膨大な遺稿から、『要綱』デッサン通りに第2部と第3部をエンゲルスがまとめたのだから、これは体系構成研究から除外してよい。
旧構想をそのまま踏襲したということは、経済学体系がどうあるべきかをエンゲルスが読み取ることができなかったことを意味している。エンゲルスが元にしたマルクスの資本論構想は1858年の『要綱』で示されていたものである。フランス語版の出版が1872年だから14年も間がある。
フランス語版編集時点で全体の見通しがあったかどうかはわからない。マルクスは構想を大きく変えたか、見通しがまったく立たないままだったかのどちらかだが、資本論第2部の編集方針については何も書き残していない。それゆえわたしたちは『要綱』『資本論初版』そしてマルクスが編集を直接指示したフランス語版の「第一部」の内容から、内在的な論理に従って体系構成がどうあるべきかを読み取らなければならない。
ヨーロッパの学問の伝統という点からは、科学の方法(=人文科学をも含む学問の方法)にはアリストテレス論理学とユークリッド「原論」が燦然と輝いている。経済学の体系構成を考えるということは、そういうヨーロッパの学問の伝統線上にマルクス『資本論』を措定したときに何が見えてくるのか、という問題でもある。
『資本論』は経済学的概念の構造物なのだが、書かれた文章から使われているいくつかの概念の関係を抽象的な構造物としてイメージするのはむずかしい。言葉をイメージに変換するのにハードルが一つあり、さらにそのイメージを今度は別の具体的な言葉に変換して説明するために、もう一つのハードルが待ち受けている。ひょんなことから、ユークリッド『原論』を読み、数学の体系と経済学諸概念の体系が似ていることに気がついた、これなら、アナロジー(類推)が可能だし、説明も楽になる。修士論文を書いていたときにそのことに気がついていたら、大学に残る決意を固めただろうが、不勉強で気がつかなかった。
2. <体系構成法の視点から見たユークリッド『原論』>
高校生には「ユークリッドの互除法」が教科書に載っているから馴染みがあるだろう。ユークリッドの人物についてはどこで生まれてどこで育ったのか、記録が残っていない。しかし、実在したことだけは確かである。アルキメデス(287年ごろ~212B.C.)がその著「『球と円柱について』の第1巻の第2命題の証明の中で「ユークリッド(の『原論』)の第1巻命題2により」と記してある。
(ユークリッド『原論』より、「ユークリッドと『原論』の歴史」437㌻。訳・解説 中村幸四郎・寺阪英孝・伊藤俊太郎・池田美恵 共立出版社1971年初版、以下『原論』と略記)
ユークリッドはイデア論で有名なプラトンの直弟子たちと同世代である。
『原論』は公理・公準の説明に続いて、同じ半径の円を二つ使った正三角形の作図から幾何学の解説を始めている。第1巻は平面図形の性質がとりあげられている。『原論』は平面幾何学だけではない、数論や立体幾何学、正多面体にまで及ぶ。第7~9巻は「数論」を扱っている。ここで面白いのは、線分の長さの区切りに数字ではなく文字が充てられている点で、広義の意味での代数学も含まれていると考えてよいのだろう。第7巻の冒頭には23個の定義が並んでいる。大雑把にその順序を書くと次のようになる。
単位⇒数⇒割り切れる数と割り切れない数⇒約数⇒偶数と奇数⇒偶数や奇数の除算の商の分類⇒素数の定義⇒互いに素⇒素数と合成数⇒平面数:二つの数の積で表される数⇒立体数:三つの数の積で表される数⇒平方数:等しい数に等しい数をかけたもの⇒立法数⇒比例数⇒相似な平面数と立体数は比例する辺をもつ数である⇒完全数:自分自身の約数の和に等しい数
数論の定義は単純なものから複雑なものへという順序で並んでいる。
最終巻の13巻第16章では正二十面体がとりあげられている。
「正二十面体をつくり、先の図形のように球によって囲み、そして正二十面体の辺が劣線分とよばれる無理線分であることを証明すること」(『原論』427頁)
立体図形、しかも正二十面体の辺が有理数ではなく無理数であることを証明せよというのである。球の直径を有理線分(有理数)としたときに20個の等辺三角形(正三角形)の各辺の長さが無理線分(無理数)になる証明が載っている。
『原論』は平面幾何学と数論そして立体幾何学に及んでいる。全体が統一の取れた体系というよりは、いくつかの部分に分かれているといったほうが事実に即しているだろうか。全体の展開順序はこのようになっている。
平面幾何⇒数論⇒立体幾何
平面幾何と立体幾何の間に数論の挟まっているのがどうにも不細工にみえるが、数論を扱わぬわけにもいかない。平面図形の中に、無理数の背理法での証明や三平方の定理が載っているが、数論として独立に扱えるものではなく、平面図形に付随して扱われただけ。計算が複雑になるに及んで、立体図形の前に数論として独立に扱わざるを得なくなったという事情があるのだろう。
平面に高さという要素を加えたものが立体であるから、単純さを尺度にすると、次の不等式が成り立つ。
平面図形<立体図形
ここでも単純なものからより複雑なものへという展開系列の順序が守られている。
第1巻の平面幾何は、重なり合う半径の同じ二つの円で等辺三角形を描くことから始められている。平面を二つの線分で囲むことはできない、三本の線分で囲まれた三角形がもっとも単純な平面図形である。三角形の内では等辺三角形がもっともシンプルで美しい。三角形を3分類して並べると、「等辺三角形⇒二等辺三角形⇒不等辺三角形」の順序になるが、第1巻は等辺三角形のあとに三角形の等積変形が来て、そして平行線の性質が導かれている。
マルクス『資本論』との関係でいうと、注目すべきは公理・公準と作図の展開順序の2点に絞られる。第1巻の図形の性質は、もっとも単純な平面図形、(半径の同じ円二つを使った)正三角形の作図が最初におかれている。数論の定義の並び順も「単純なものから複雑なものへ」という系列になっていることはもうお分かりだろう。
第1巻は「定義」⇒「公準」⇒「公理」⇒単純な図形の作図(正三角形)という順に展開されている。定義は23個あり、公準(要請)は5個、公理(共通概念)は9個並んでいる。定義は「点⇒線⇒線の端⇒直線⇒面⇒平面⇒…⇒平行線」
体系構成で最も重要な公理・公準はユークリッド『原論』では次のようになっている。
公準(要請) 次のことが要請されているとせよ。
1. 任意の点から任意の点へ直線を引くこと。
2. および有限直線を連続して一直線に延長すること。
3. および任意の点と距離(半径)とをもって円を描くこと。
4. およびすべての直角は互いに等しいこと。
5. および1直線が2直線に交わり同じ側の内角の和を2直角より小さくするならば、この2直線は限りなく延長されると2直角より小さい角のある側において交わること。
公理(共通概念)
1.同じものに等しいものはまた互いに等しい。
2.また等しいものに等しいものが加えられれば、全体は等しい。
3.また等しいものから等しいものがひかれれば、残りは等しい。
4.また不等なものに等しいものが加えられれば全体は不等である。
5.また同じものの2倍は等しい。
6.またおなじものの半分は互いに等しい。
7.また互いに重なり合うものは互いに等しい。
8.また全体は部分より大きい。
9.また2線分は面積を囲まない。
同書2頁より
平行線公準が成り立たないものと前提すると、リーマン球面幾何学のような非ユークリッド幾何学が成立することから、『資本論』の公理・公準の一部を入れ替えると別の経済学が生まれる可能性があることは容易に予想がつく。そういう操作を大学院生の頃から考えていたが、当時は何をどのように換えたらいいのかわからなかった。
中学校と高校の図書室にはこのユークリッド『原論』を備えてもらいたい、そして数学の先生はそういう本が自分の学校の図書室にあることを生徒に伝えてもらいたい。数学好きの早熟な生徒なら十分に読める。田舎の学校でも、工夫次第で都会の学校よりもいい環境を整えることができる。大人の責任を果たすために、できることから始めてもらいたい。
3. <マルクスが『資本論』で何をやりつつあったかを読み解く>
マルクスが資本論で何をしようとしたのかについては定説がない。マルクス自身が資本論第1部を書いて、そのあと草稿を書き散らしただけで、どのようにまとめたらいいのかわからないと吐露している。だから、1858年に書かれた『要綱』段階のマルクスの構想で資本論を整理してはいけない、マルクス自身が1866年に体系の見通しが立たなくなったとエンゲルス宛に書いているのだから、その言を尊重すべきであり、マルクスがなぜ行き詰ったのかを合理的に説明できなければならない。この大きな謎を解いた経済学者はいない。謎を解く鍵はヘーゲル弁証法にある。経済学体系構成にヘーゲル弁証法を利用したのはプルードンとマルクス二人だけである、後にも先にも例がない。
マルクスは研究が行き詰ったことをエンゲルスへの手紙で吐露しただけだから、彼が資本論で何を目論んだのか本当のところがわからないままである。だから、エンゲルスが古い構想に基づいて第2部以降を編集したように、他の経済学者が資本論を読んで独自の理論体系を構築する余地が残された。
たとえば、マルクス経済学では宇野シューレが最大派閥であるが、宇野弘蔵は理論構成を三段階(原理論・段階論・現状分析論)に分け、資本論を経済学原理論と位置づけた。『要綱』日本語版が出版されていない段階での研究だから、マルクスがやって見せた下向分析の過程を丹念に追わずに、結果の『資本論』を徹底的に読み込んで自分なりの思考を重ね、別の理論体系をつくってしまった。これはこれで面白い。宇野氏は『資本論初版』序文にある、次の章句を何度も読み返し、塾考を重ねたのだろう。
「物理学者は、自然過程を観察するにさいしては、それが最も内容の充実した形態で、しかも撹乱的な影響によって不純にされることが最も少ない状態で観察するか、または、もし可能ならば、過程の純粋な進行を保証する諸条件の下で実験を行う。この著作で私が研究しなければならないのは、資本主義的生産様式であり、これに対応する生産関係と交易関係である。その典型的な場所は、今日までのところイギリスである。これこそは、イギリスが私の理論的展開の主要な例解として役立つことの理由なのである。」
マルクスの『資本論』を読めば読むほど迷路を彷徨うことになる、わたしは高校2年生のときにそういう強烈な体験をした。大きな森の中に入り込んで方角を失ったのである。それ以来、この巨大な知の森にもう一度分け入り、通り抜けてみたいと思い続けた。見通しがつくまでなんと約40年も掛かってしまった。
大御所の宇野弘蔵はマルクスが『資本論』を書いている途中で、肝心の体系構成の方法論で破綻したとは考えなかった。マルクスは『資本論初版』第一部を書き上げて、自分の方法論の破綻に気がついてしまった。だから、エンゲルスに第2部以降の体系化はとても無理だと手紙で書き遺したのである。実際に第2部以降の体系化作業をやることはなかった。
マルクスの時代には資本の原始蓄積が始まったのは18世紀英国で、資本主義の最初の典型例であった。その後百年たった19世紀中葉の米国では北部工業地帯で原始蓄積が始まり、南部の奴隷を工場労働者として労働市場へ投入する必要が生じた。いま資本の原始蓄積過程にあるのは中国やインドである。原始蓄積が始まれば、労働者の雇用数が増大し、賃金が高騰する。だが、それは資本蓄積を阻害することのない範囲であるとマルクスは「第七編 資本の蓄積」で指摘している。資本蓄積の進行は労賃変動の根源である。英国が研究対象となったのは当然である。
宇野『価値論』は読むほうが辟易するくらいしつこいが、しつこいからこそ独自の理論体系を造り、大きな学閥となりえた。わたしは宇野氏の『価値論』の論理展開しつこさに辟易すると同時に敬意を払いたい、たとえ見当違いの方向に行ったとしても、学者はあれぐらいしつこくなければいけない。
宇野弘蔵『経済学方法論』について、宇野学派の馬場宏治先生が感想をもらしている。
---------------------------------------------------------------------
「方法論なんてものもね、型にはまった図式化できるのが方法論だとは僕は思っていない。俺何やってきたってあとから考えてみて、こうなっていたのよってのが方法論じゃないかと思う。宇野先生の『経済学方法論』、宇野さんの書いた中で一番つまらない、あれは病気のせいもあるだろう。だけどそうじゃないんで宇野さん、本当の方法論書こうと思ったからしんどかったんじゃないか。教科書風な、変な書き方、堅い書き方になっていますよね。」(青森大学研究紀要第33巻-第1号 2010年7月「社会科学を語る(続)」馬場宏治・戸塚茂雄)
「方法論なんてものもね、型にはまった図式化できるのが方法論だとは僕は思っていない。俺何やってきたってあとから考えてみて、こうなっていたのよってのが方法論じゃないかと思う。宇野先生の『経済学方法論』、宇野さんの書いた中で一番つまらない、あれは病気のせいもあるだろう。だけどそうじゃないんで宇野さん、本当の方法論書こうと思ったからしんどかったんじゃないか。教科書風な、変な書き方、堅い書き方になっていますよね。」(青森大学研究紀要第33巻-第1号 2010年7月「社会科学を語る(続)」馬場宏治・戸塚茂雄)
方法論については馬場先生のいう通りだと思う。マルクスもヘーゲル弁証法を真正面に押し捲ったが、研究が進んでくるとヘーゲル弁証法とは違うところにでてしまった。あとから自分の研究過程をみて、方法はこうだと書けばよかったのだろう。そこでマルクスに代わってその作業を試みるのがこの論考の主要な目的の一つである。
宇野氏が数学に興味があるかあるいは『要綱』が出版されていれば、丹念に読んで別の理論体系を構築した可能性はある、それにしても、宇野氏はドイツ語を読むのにそれほど困難があったわけではないから、『要綱』をドイツ語版で読めばよかったのだ。『経済学批判』と『資本論』を読んでいれば十分だと判断したのだろうか、わたしにはその点が疑問である。
4. <資本論体系の特異性とプルードン「系列の弁証法」>
一番大事な点:資本論は数学と同じ演繹的体系をなしている。
経済学が経験科学なら、データに基づいて帰納的に法則を導き出し、理論を構築するのという方法論をとるはずだが、マルクスはそうはしなかった。はじめに方法論ありきだった。
経済学の研究という点から見るとじつに運のよいことにマルクスは1849年に英国に亡命し、1850年から大英図書館で経済学の研究をし始める。A.スミス『諸国民の富』やD.リカード『経済学および課税の原理』はよく読みこんでいる。経済学の本を読み、経済学の基本概念はなにか、その相互関係はどうなっているのかということに関心をもち何年間も執拗に追い続けたようで、その跡が著作年表や一連の著作から読みとれる。1858年『経済学批判要綱』(以下『要綱』と略記)での、「流通過程分析⇒価値形態(価値表現形式)⇒商品の基本概念分析」に下向分析の足跡がはっきり記されている。資本の原始蓄積過程における生産性上昇による生産力増大、そして資本の加速的な増殖が労賃の高騰を招くというような法則性抽出は、データの読みと内省的な思考の結果である。
ヘーゲル哲学にとらわれすぎると、それを超えたところにある『資本論』体系が見えなくなる。ヘーゲル哲学に戻って考える必要はない。『資本論』第1部をよく読めばいいのである。
方法論に注目すると、同時代のピエール・ジョセフ・プルードン(1809/1/15-18651/19、マルクスより9歳年上)に系列の弁証法がある。プルードンの論理的系列は思考作用の抽象過程をあらわすものであると同時に、「その結果としてえられる抽象的・一般的な概念の構造を表す」(佐藤茂行著『プルードン研究』109ページ、昭和50年出版)ものであると考えていた。アンダーラインを引いた箇所は、そのまま『資本論』に当てはまる。
プルードンはフランス人だからデカルト『方法序説』(いまでも高校国語の教材に採り上げられている)は読んでいるはずで、その延長上に自分の思考を積み重ねたのだろう。デカルトよりは踏み込んでいる。弁証法がこの時代の流行だったのだろう、しかし、ヘーゲル弁証法という余計な夾雑物が混じることで上向の論理の道をプルードンもマルクスも踏み外してしまった。
A.スミスが諸国民の富の原因と性質を明らかにするものとして経済学を捉えたのに対してプルードンは貧困を実証する手段として捉えた。そして自らの経済学体系を「系列の(ヘーゲル)弁証法」で叙述したのである。
---------------------------------------------
「「経済学」を貧困の原因の探求の科学としてではなく、貧困の実証の科学として評価するに至ったのであった。言いかえると、これまでの経過から判明するように、プルードンが経済学研究に取り組んだ際の問題関心は、現実的な「条件と財産の不平等」の究明であった。パリでの研究を通じて、かれにとって「経済学」は、この「不平等」の原因を究明する手段ではなく、これを実証する手段として、そしてその限りで有効なものとして評価されるに至ったわけである。」同書188ページ
「プルードンの経済学体系は、平等=正義を分類主題として、「政治経済学」のカテゴリーを批判的に再編成した、いわば古典経済学批判の体系である。そこでは、まず、「分業」「機械」「競争」などのカテゴリー(類概念)が、平等=正義を区分原理として、それに対する肯定と否定の規定(種概念)にあらかじめ二分されている。…このようにして、相互に「アンチノミー」の関係にある概念の系列、すなわち「矛盾」の体系が成立する。…以上のような体系の構成の原理は、1843年の『人類における秩序の創造について』の中の「系列の弁証法」によって確立していたのであった。」同書238ページ
---------------------------------------------
アンダーラインを引いたところは『資本論』商品章の価値と使用価値が相互にアンチノミーの関係にある概念として扱われ、価値形態でそれが交換価値と使用価値という概念の系列となって現れている。しかし、一連の著作の中でマルクスは系列の弁証法に一度も言及していない。プルードンの『人類における秩序の創造』(以下『創造』と略記)は資本論初版よりも24年も前に書かれている。マルクスが最初の経済学に関する著作『経済学・哲学草稿』を出版したのが26歳1844年、つまりプルードンの『創造』の1年後のことになる。プルードンのこの著作のドイツ語版があったのかどうかは書誌学者の研究に任せたい。
方法論としてはほとんど同じであるのに言及していないというのは、この場合は利用したと受け取っていいのだろう。シンプルに言うと、プルードンの「系列」とは上向の系列であると理解してよい。マルクスが上向論理で行き詰ったのは、系列の弁証法を意識したか、同じことだがヘーゲル弁証法を『資本論』の論理展開エンジンに用いたためであるように思う。それはまったく必要のないことだった。
アナーキストのプルードンとは、思想においても方法論においても、コミュニズムを提唱したマルクスは明確な線を引いておきたかったのではないか。マルクスは古典派経済学から学び、その基本的な概念を析出しそれらの相互関係を突き止める作業が必要だった。そこさえきっちり押さえれば、系列の順序はおのずから明らかになった。『要綱』がそういう研究過程を明らかにしてくれているから、プルードンの系列の弁証法から学ぶ必要はなかった。
『資本論』研究文献でプルードンの系列の弁証法に言及したものを見たことがない。体系構成についてプルードンとの比較分析の余地がある。
ついでだから、もうすこし掘り下げて具体的に論じてみたい。1866年のエンゲルス宛の手紙にあるように、マルクスには上向の系列が途中から見えなくなったことがわかる。事実に即して言えば、交換関係から貨幣を媒介として生産関係へと概念的関係を拡張した後、どのように体系を記述すればいいのかわからなくなった。下向分析で見つかった上向系列が生産関係で行き止まってしまった。単純な市場関係を展開した後、「国内市場と国際市場」関係へと概念的関係を拡張し、世界市場関係へと至る道がマルクスの採るべき上向系列だった。ところが、資本論初版が出版された1867年にはまだ世界市場は出現していない、そこに気がついて困惑した可能性がある。マルクスの時代に『資本論』を完成することは無理だった、世界市場は実証研究がその背後になければ描きえないのである。あの時代にはリカードの比較生産費説があるだけだったが、それで世界市場を描くことはできない、貧弱すぎるのである。この点から、経済学は経験科学の一つで、なおかつ演繹的体系構成をもつ面白い学問分野であることがわかる。
院生のとき、リカードの国際市場論について小論を書いた。その折にマルクス『資本論』と比較しながらリカード『経済学および課税の原理』を読んだ。修論で『資本論』の体系構成の最後の環である世界市場関係に見通しをつけるために、リカードの国際市場論は一度読んでまとめ、中身の検討をすべきだと考えていたのだが、単純な国際市場関係とその完成形態である世界市場関係を概念的に区別するとしたらどうなるのかまったく見通しが立たなかったのである。もちろん、今日のグローバリズムや機械とコンピュータとインターネットが融合したサイバー空間が現実の世界にあるはずもなく、不可能だったと言わざるをえない。そのころからマルクスの労働観への違和感も大きくなりつつあった。
5. <労働観と仕事観:過去⇒現在⇒未来>
奴隷制社会と農奴制社会を経験しているヨーロッパおよび中国、借金を返済できずに隷属民となる例はあるが奴隷制社会を経験していない日本は労働観に決定的な違いがあることを指摘しておきたい。労働は苦役であるというのは特殊ヨーロッパ的あるいは中国的な労働観であり、普遍性をもちえない。それぞれの地域において歴史的にさまざまな労働観が育まれたのだろうと思う。
古代ギリシア都市国家においては労働をするのは奴隷だった。特権市民は労働しない。その伝統は帝政ローマへも引き継がれた。こうしたヨーロッパの歴史が労働への蔑視を生んだのではないか。
わが国では国が成り立つ以前の縄文時代から続いている村落共同体のあり方も、働くことや仕事に対する考え方の違いを生み出したように見えるので、横道にそれて第23章「村落共同体と税:自由民と農奴」で取り上げる。
古代エジプトやメソポタミア、インド、中国ではどうだっただろう。こういう風に並べてみると「特殊ヨーロッパ的な労働観」の意味がいっそう鮮明になる。
この小論のテーマに関連する限りでは、ヨーロッパの労働観を取り上げるだけで十分だろう。
【過去系列】
(1) 古代都市国家およびローマ帝国での特権市民と奴隷や農奴
(2) 初期:東ヨーロッパ人の奴隷化:貿易支払いのための奴隷狩り
(3) アフリカ人の奴隷化
(4) 第一次産業革命
(5) 米国南部での奴隷需要増大
(6) 米国北部工業地帯で労働力商品の不足状況の現出 奴隷解放(1862年)=安価な労働力商品として黒人奴隷を解放して、北部工業地帯の労働力需要を満たす⇒ 米国の生産力の飛躍的拡大と世界支配開始
(7) 資本主義の第2段階開始:米国の勃興と白人帝国の世界支配の時代⇒帝国主義と植民地化政策資源収奪や低価格での一次産品収奪のための植民地政策。
(8) 白人帝国主義国家対アジアの戦い:日露戦争で有色人種の国が白人帝国に世界初勝利 (9) 大東亜戦争での日本の敗北と、日本の戦いに意を強くしたアジア各国が白人大国から次々に独立。
【現在進行系列】
(10) グローバリゼーションの時代:米国製ルールの押し付け
(11) 第二次産業革命:機械とコンピュータとインターネットが融合する時代。それ以前に比べて工場の生産性が数十倍になる。企業間競争の主戦場はソフトウェアとサイバー空間へ移る。
(12) 東アジアとインドへ覇権がシフトしていく
【未来系列】
(13) 第三次産業革命の時代(百年後):量子コンピュータネットワークの世界。
現在の性能向上速度を延長すると、コンピュータの性能は百年後に現在の2億倍になる。物の生産に人間の手は要らない時代となる。現在のコンピュータの2億倍の性能を持つ人工知能がわずか5cmのキューブサイズになる。ネットワークにつながれた人工知能とロボットが工場生産のすべてを支えるから、生産に人間が邪魔になる時代、人間の存在理由がなくなりかねない危ない世界でもある。どれほど優れた人間よりも、人工知能搭載人型ロボットのほうがはるかに性能がよい製品をつくり、さまざまなサービスを提供する世界が現出してしまったら、人間は労働者でも職人でもいられなくなる。コンピュータの処理速度や記憶容量が2億倍にもなってしまったら、人工知能搭載の人型ロボットと競争しても、性能の面でもコストの面でも人間が勝てるわけのない時代の幕が開けてしまう、百年後の人類はどうやって職を探すのだろう?量子コンピュータがパンドラの箱を開ける鍵でないことを願うが、便利さを追い求め、欲望の拡大再生産を続ける人間が自らの手で経済成長や利便性追及を止めることができるのだろうか?強い懸念を表明せざるをえない。
こうして過去・現在・未来の系列を俯瞰してみると、無限に自己増殖する資本はまるで癌細胞のようで、未来が人類にとってこういう風に悲観的なものだとしても、わたしたちは資本の自己増殖をとめることができるのだろうか?
資本の増殖の背後には人間の欲望の無限の自己増殖があるのだが、人間のコントロールを超えて資本が自己増殖する時代がコンピュータとネットワークの進化によって百年経たないうちに来る。
過去30年間のコンピュータの計算速度とメモリーの拡大速度を前提にすると、おおよそ百年後に処理速度も記憶容量も2億倍になり、コンピュータもネットワークも人間のコントロールを離れてしまう。コンピュータとネットワークとそれに接続されたさまざまな機械が人間のコントロールを離れて自立的に動く世界、そしてそれをとめるすべはおそらく人間にはない。
これから一世代、どんなに遅くとも二世代の間に、小欲知足の価値観に基づき、肉体を使う仕事へ回帰して、過剰な便利さを排除する、職人中心の経済社会を創るべきなのだろう。無限の成長は癌細胞の成長そのものである、経済成長を追い続けることをやめるべきだとわたしは思う。
その一方で、生物進化が必然だと仮定すれば、人類は経済成長と利便性の追及の果に絶滅する運命にあるのではないかとも考える。人類には自らの欲望を抑える叡智があるだろうか。
5. 数学者藤原正彦氏の示唆
数学者とはすごいものだ。慧眼の数学者は岡潔だけではなかった。一つの学問分野を深く掘り抜けば、他の分野へも通底するものがある。
藤原正彦はA.スミスの経済学へ次のような根本的な疑問を投げかけている。わたしは経済学にこのような根本的な疑問を投げかけた経済学者を寡聞にして知らない。
(アダム・スミスの)予定調和でこの社会が巧く回っていく、と。しかし、そこにあるのは結局は経済の論理だけなんです。人間の幸福ということはどこにもない。市場経済もまったく同じです。いま、何をするにも「消費者のため」と言いますよね。消費者がよいものを安く買えることがもっとも大切だ。たとえばお米を安くするためには自由貿易を推進してお米をどんどん輸入するのがよい。そうすると日本から百姓はいなくなって、美しい田園が全部なくなってしまいますが、そうなっても仕方がない。消費者が半分の値段でお米を買えればいいじゃないかと、そういう論理です。
はっきり言ってしまうと、経済学の前提自体が根本的に間違っている。人間の幸福ということは全く考慮にない。人間の金銭欲のみに注目し、個人や国家の富をいかにして最大にするしか考えていない。ものすごい天才が出てきて、経済学を根本的に書きかえてもらわないと、地球はもたないと思います。
産業革命以来、西欧は論理、合理を追求しすぎて、「人間の幸福」ということを全部忘れてしまった。(106ページ)
この箇所を読んだとき、日本の経済学者は誰一人このことに気づいていないのに、なぜ数学者である藤原正彦氏が気づいたのか、その目の確かさに驚いた。
ユークリッド原論は数学者の常識に属するから、経済学の出発点の誤りが体系全体の及んでいるというのは学問体系の相似性から言いうることで、むしろ当たり前のことだったが、経済に関心をもつすぐれた数学者がいなかった。
その一方で次のような疑問がわく。経済学者、とりわけ日本の経済学者はなぜこのことに気づかなかったのだろう?
簡単に言えば自分の頭で考えていないからだろう。ある種の能力がないとも言い切ってよいかもしれない。スミスやリカードの目でしか経済現象を見ていない、誰一人自分の目で見ていないのである。どこか学問をやる根本的な視点がずれている。経済学に限らずそういう「学者」が多いのは事実だろう。話はそれるが林望『知性の磨き方』(PHP新書)を読んだときにも、学問への姿勢に違和感を感じた。
「#969 日本人の矜持(2):経済学への示唆」より転載
=================================
* #1454 異質な経済学の展望 :パラダイムシフト Mar. 31, 2011
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2011-03-31
#2784 百年後のコンピュータの性能 Aug. 22, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-08-22
#2779 『ソードアートオンライン 9 』:量子コンピュータ・オンラインゲームと心 Aug. 17, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-08-17-1
#2804 『ソードアート・オンライン14』 Sep. 12, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-09-13
#2882 ソードアートオンライン007 マザーズロザリオ Nov. 26, 2014
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2014-11-26
#3217 日本の商道徳と原始仏教経典 Jan. 7, 2016
<8/2 ポイント配分割合変更>
100% 0% 0%
2015-08-02 22:16
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0